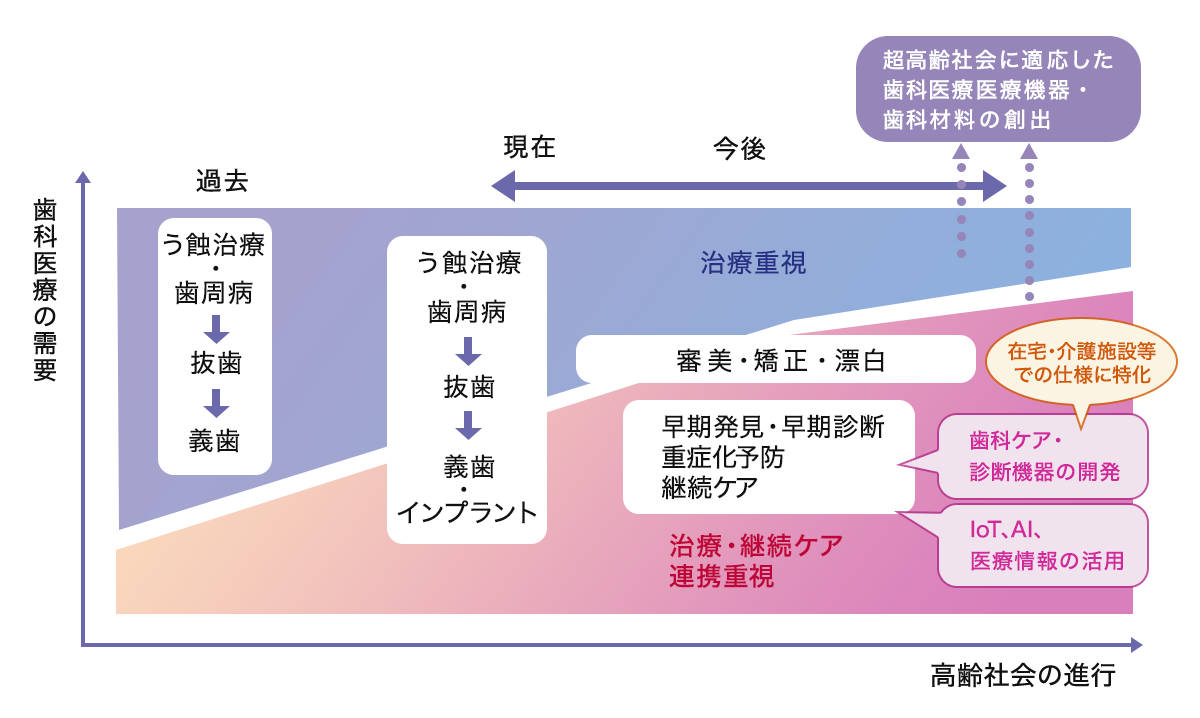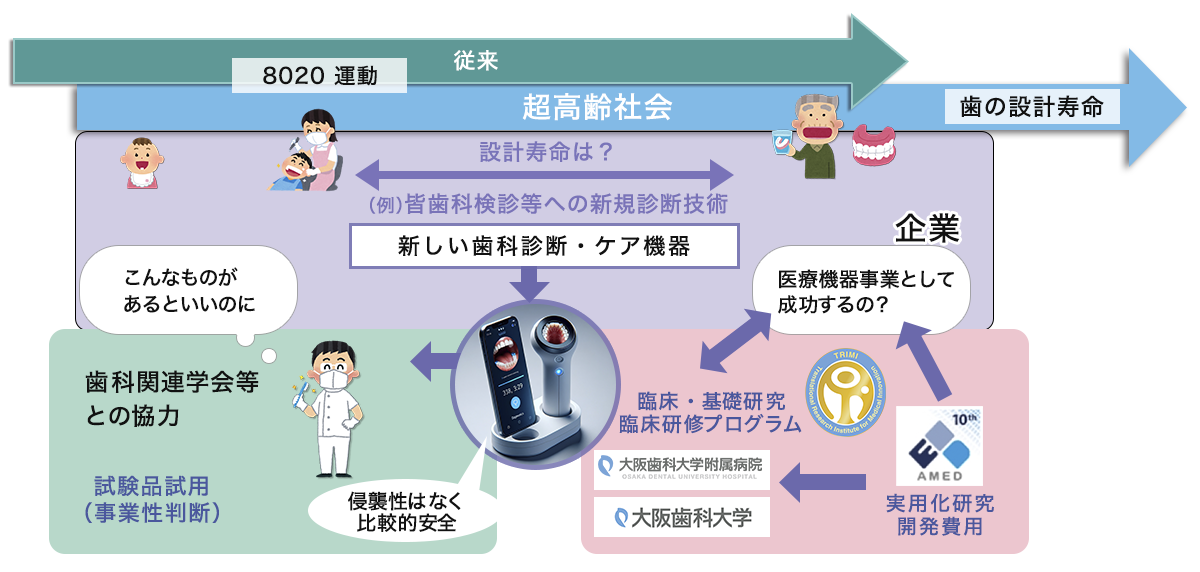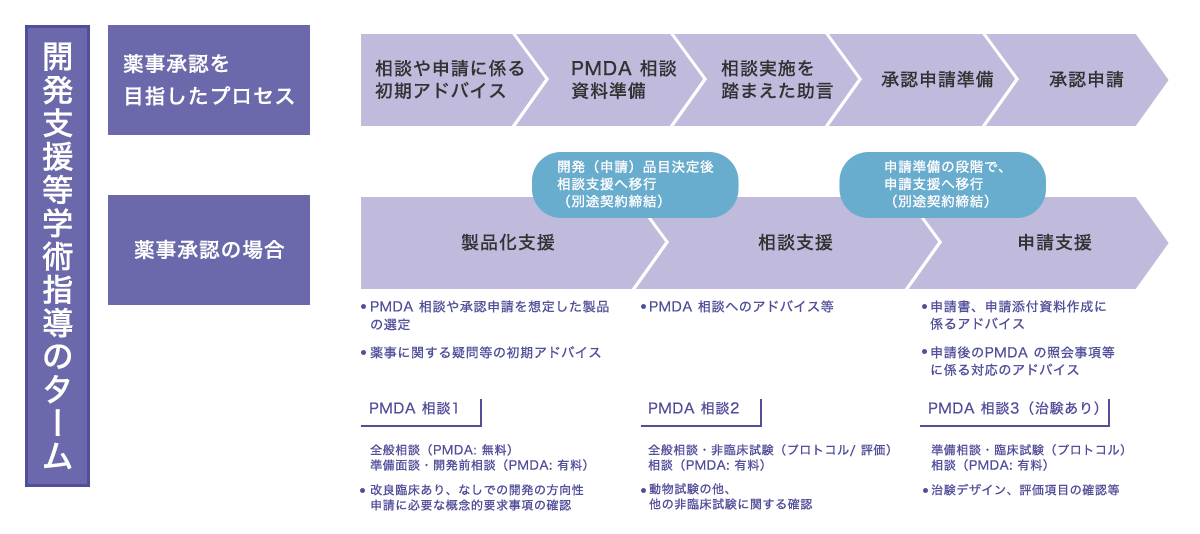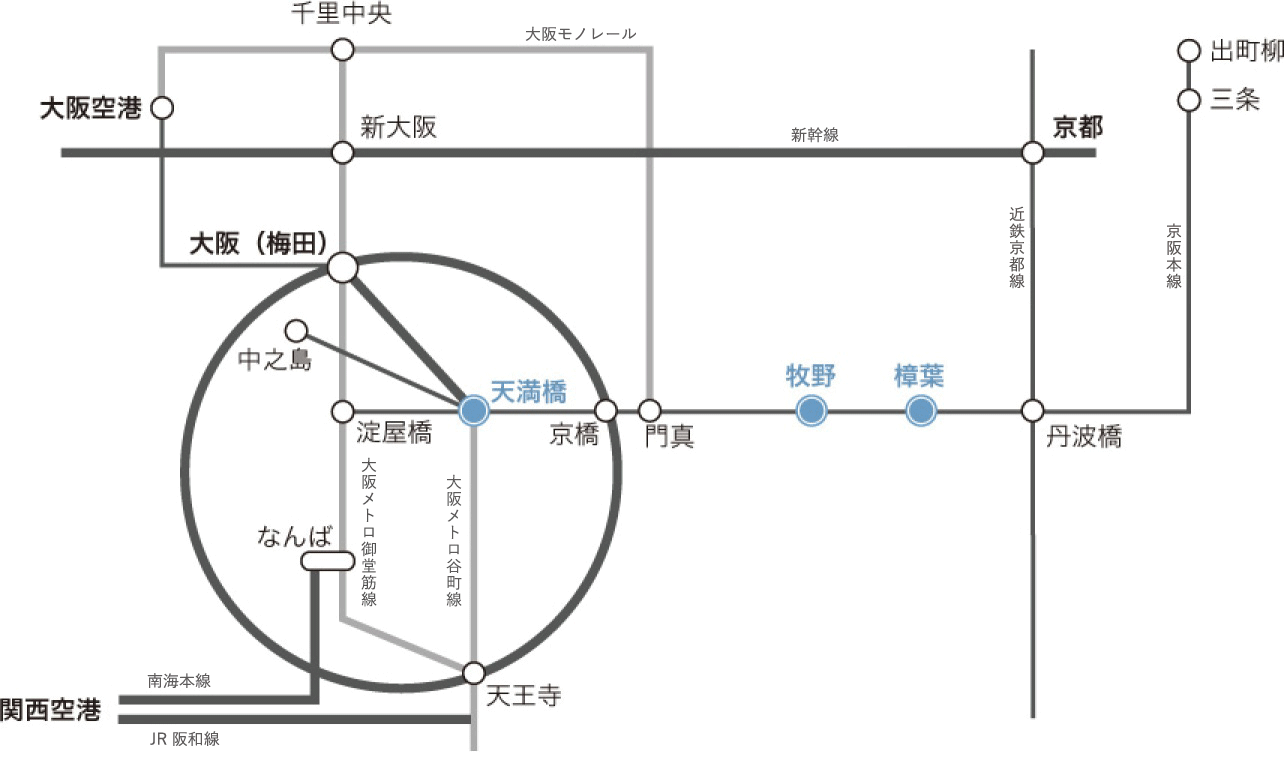優れた歯科医療機器・
材料開発の気付きを目指す
臨床研修プログラム
入門コース
(研修期間:4ヶ月程度)
歯科医療全般にわたっての基本診療の流れを修得するとともに、用いられている医療機器の効果効能等の特性、使用感、使用頻度、収載されている保険点数、若しくは自費の場合は自費診療に関わる費用の算出方法を研修するコースです。
応用コース
(入門コース修了者対象)
- (1)データ管理コース
(研修期間:6ヶ月程度)
大学病院の保有する医療情報等のビッグデータをデータ項目毎に解説し、ビックデータの分析手法及び活用方法を修得するとともに、データから新たな医療機器開発に繋がるヒントを読み取る方法についてグループワークを通じて修得するコースです。
- (2)デジタルワークコース
(研修期間:6ヶ月程度)
デジタルワークフローについて理解し、情報の送受信におけるセキュリティー対策、或いは CAD/CAMやスキャニング等の情報通信関連の革新的な医療機器の開発に繋がるスキルを修得するコースです。
- (3)マテリアル開発コース
(研修期間:9ヶ月程度)
臨床に使用されている体内埋込型の医療機器のマテリアルについて、機器毎にそれぞれの特性を修得するコースです。
- (4)口腔ケア・リハビリテーションコース(研修期間:9ヶ月程度)
摂食嚥下障害や口腔機能低下症で口腔リハビリテーション科に来院されている患者や、病院と連携する老人保健施設に入所されている患者を対象として、現在行っている検査・診断と治療、特に直接的・間接的嚥下訓練や口腔リハビリテーションの流れを研修するコースです。
各コース共通の修得事項
- 患者の同意の下で診療のオブザーバーとして立ち合い、患者の受診から検査・診断、治療までのプロセスを学ぶことができます。また、特定の医療機器が使用される現場も経験し、その使用方法や患者への影響を観察することができます。
- 医療専門職の講師から、医療機器の要件定義、デザイン思考、患者中心の開発アプローチについて学ぶことができます。
- 医療現場の実際のニーズの特定と技術開発とのギャップを理解し、新たな医療機器のアイデアを生み出すスキルを習得することができます。
- ブレインストーミングやデザイン思考の手法を用いて、患者ニーズを満たすための新たな医療機器のアイデアの提案から、プロトタイプの計画、そして実現可能性の評価に至る製品開発過程についてグループワーキングを中心とした研修を通じて具現化させるスキルを修得することができます。
臨床研修プログラム・
事業分担
馬場 俊輔
大阪歯科大学
医療イノベーション研究推進機構(TRIMI)機構長
大阪歯科大学附属病院
副病院長
大阪歯科大学 口腔インプラント学講座
主任教授